信頼性解析と不具合の未然防止(1)
実験の目的
この実験項目では,FMEAとFTAという二つの信頼性解析手法を修得します.FMEA(Failure Mode and Effect Analysis)は,製品を構成する部品やサブシステムにどのような不具合が発生するかを予測し,それが製品やシステムにどのような影響を及ぼすかを把握するための手法です.重大な影響を及ぼす不具合を未然防止するには,どのような改善を行えばよいかも検討します.
FTA(Fault Tree Analysis)は,製品やシステムに発生してほしくない事象について,論理記号を用いて,その発生の経過をさかのぼって樹形図を展開し,発生経路及び発生原因,発生確率を解析する手法です.
この実験では,FMEA,FTAという手法の使い方とともに,両手法の違いについても理解することを目的としています.
FMEA
まず,本実験で用いるFMEAについて説明します.FMEAとは,Failure Mode and Effect Analysisの略で,日本語では故障モードとその影響解析と訳します.設計の不完全な点や潜在的な欠点を見出すために,構成要素の故障モードとその上位アイテムへの影響を解析する技法です.故障モードとは,故障状態の形式による分類です.例えば,断線,短絡,折損,摩耗,特性の劣化などです.故障メカニズムが故障に至る物理的・化学的過程を意味するのに対して,故障モードは故障がどのような状態で生じていたかを示します.故障メカニズムが不明の場合でも故障モードは観測可能です.言い換えれば,観測可能な故障の状態が故障モードです.
FMEAでは,システムや製品のサブシステム・部品に発生すると考えられる故障モードを列挙し,その故障が起こった場合システムや製品にどのような影響を及ぼすかを解析します.さらに,故障の発生する原因,故障検知法などを検討し,その結果信頼性を損なう可能性の大きい故障モードを設計段階で除去します.
FMEAの一般的手順
以下にFMEAの一般的手順を示します.
|
FMEAの一般的手順 (1)FMEAを実施しようとするシステム,サブシステムの任務(構成品の機能など)を確認する. (2)FMEAを実施しようとするシステム,サブシステムなどの分解レベルを決める. (3)機能図,システム明細書などを調べて,それぞれ機能別ブロックを決める. (4)機能別ブロックからサブシステムの信頼性ブロック図を作成する. (5)ブロックごとに故障モードを列挙する. (6)列挙した故障モードを整理して,FMEAの実施に効果的な故障モードを選定する. (7)選定した故障モードごとに推定原因を列挙する. (8)FMEAの記入用紙に要約を書き入れる. (9)設計条件,致命度分類基準を参照しながらFMEAをまとめる. (10)故障等級の高いものについて,設計変更の要否などの検討を行なう. |
この手順について,懐中電灯の例で説明します.
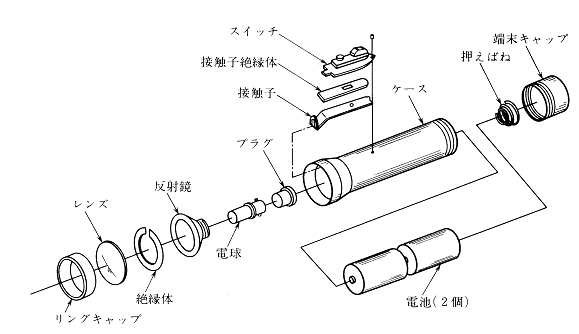
図1 懐中電灯の概念図
(1)任務
必要なときに光を出し,照明に使用する.
(2)分解レベル
部品あるいは数個の部品で構成された組立品を分解レベルとする.
(3)機能ブロック
電灯回路,光線発生部,構体の3つの機能からなる.簡単な機構であるから,機能ブロックに分解しない.
(4)信頼性ブロック図
図2に示すとおりである.
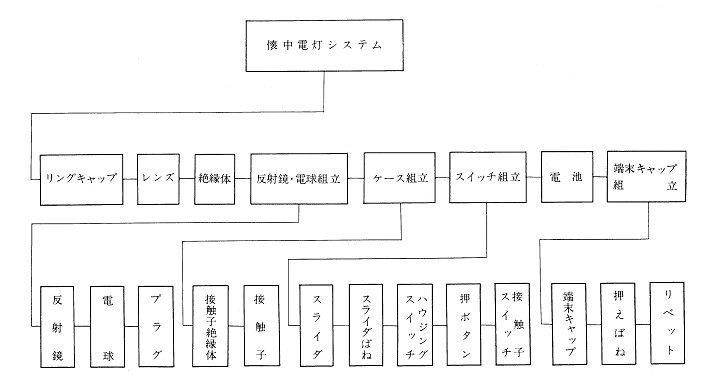
図2 懐中電灯の信頼性ブロック図
(5)故障モードの列挙
約80の故障モードを列挙することができる(省略).
(6)効果的な故障モードの選定
表1に示すとおりである.
表1 選定された故障モード
|
部品・組立品名 |
故障モード |
|
リングキャップ |
1.レンズ保持機能喪失 2.脱落 3.断面変形 |
|
レンズ |
4.脱落 5.ひび割れ 6.くもり |
|
絶縁体 |
7.切損 8.脱落 |
|
反射鏡・電球組立 |
9.電球フィラメント焼損 10.電球ゆるみ 11.電球ハンダ−電池間導通不良 12.電球・反射鏡ねじ部サビ 13.回路断(反射鏡−接触子間) 14.反射鏡がケースに入らない |
|
ケース組立 |
15.リングキャップとのねじ嵌合不良 16.端末キャップとのねじ嵌合不良 17.スイッチ取付リベットゆるみ 18.ケースースイッチ間導通不良 |
|
スイッチ組立 |
19.接触子変形 20.接触子絶縁体の絶縁不良 21.スイッチスライドせず(回路断,回路閉) 22.スイッチがケース組立より脱落 23.接触子−電池間のすき間過少 |
|
電池 |
24.電池ディスチャージ 25.電池取付不良(方向が逆) 26.電池−電球間導通不良 27.電池−電池間導通不良 28.電池−押さえバネ間導通不良 29.電池−ケース間絶縁不良 30.電池−スイッチ接触子間絶縁不良 31.電池端子サビ |
|
端末キャップ組立 |
32.押えばね機能せず 33.端末キャップ−ケース間導通不良 34.端末キャップ脱落 35.端末キャップ断面変形 36.ねじ部サビ 37.端末キャップ−ばね間導通不良 |
(7)推定原因
FMEAチャートの推定原因の欄を参照すること.
(8)FMEA記入用紙に記入し,FMEAチャートを作成する.
QCASのテンプレートでの評価点は,以下を目安とする.
[発生頻度]
10〜7:非常にしばしば発生する
6〜5:ごくふつうに発生する
4〜3:少ないけれども発生しうる
2〜1:めったに発生しない
影響と検知難易度はテンプレートのコメントをそのまま使うこと.
Excelファイル(懐中電灯.xls)にその一部を示す.
(9)FMEAのまとめ
危険優先度が200を越える故障モードのものを致命的品目表にまとめる.
(10)設計変更の検討
図面,FMEAチャートおよび致命的品目表をもとに設計変更について検討するほか,品質管理計画書,検査計画書,部品リスト,試験計画書にどのように反映させるかを検討する.
課題1
上記の事例を参考にして,FMEAを修得するために鉛筆削りを題材にしてFMEAを実施します.なお,FMEAのテンプレートは,Ntの中、もしくはStatworksのツールの中にあります.
|
FMEAの実施 (1)先の手順の(1)〜(4)を班で相談しながら実施し,信頼性ブロック図を作成する. (2)信頼性ブロック図を作成したら個人に分かれ,故障モードを列挙する.その際,班員とは相談しない.また,故障の推定原因も列挙する. (3)故障モードをすべて列挙したと判断した時点で,FMEAチャートを班員で見せ合い,不足している故障モードを補う.個人で作成したFMEAチャート,班で作成したFMEAチャートは別ファイルで保存し,差異がわかるようにしておく. (4)故障モードが整理できたならば,きびしさ,発生頻度,検出難易度を個人個人で評価する. (5)全員の評点付けが終了したら班員で見せ合い,評点が大きく異なる故障モードを抽出する.それらについてどのように評点を修正すべきか話し合い,最終的な評点を決定する. (6)評点のもっとも高い故障モードについて,その是正処置を考える.
|
以上の解析が終了したら,以下の点について考察し,レポートにまとめてください.
|
(1)個人個人で検討した時と班員と相談して最終的にまとめたときで,故障モードの数にどれぐらい差があったか,評点の異なるものがどれくらいあったかを把握する.それをもとにFMEAを実施する際の注意点をまとめる. (2)FMEAを効率的に,しかも精度よく(起こりそうな不具合を正しく把握し,未然防止を図る)実施するためには,過去の製品に関してどのような情報が整理されているいるべきか,を考察する. (3)FMEAでどの程度不具合を未然防止できるか,について考察する. |