|
この方式はある決まった量を発注するため、使用量の変化により発注の時期は変動する。
下の図は定量発注方式の型を示したものである。 この方式で基本的に決定すべきものは、発注量と発注点(発注を行う必要が生ずる在庫量の水準)である。 この方式では、在庫量が発注点に達したとき、決められている発注量を発注することになる。 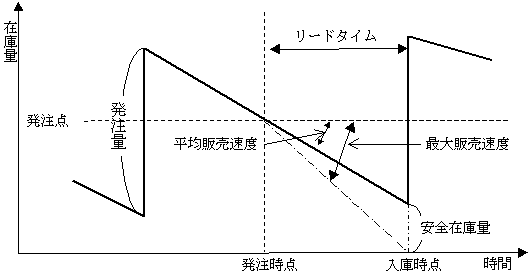 |
|
発注方式を考える場合の基本的問題として、 ①どれだけ発注するのか(発注量の問題) ②いつ発注するのか(発注時期の問題) の2点が挙げられる。この発注量と発注時期の決め方により、発注方式は以下の表のように 4つのパターンに分けることができる。
このうち、第1の「定期定量発注方式」は管理的にはすっきりしているが、 需要がかなり安定している商品にのみ適用されるので利用範囲はかなり狭い。 また第4の「不定期不定量発注方式」は、ほとんど管理体制がない方式であるので、 管理の立場から現実的ではない。 よって以下に、多くの場合利用される「定期発注方式」と「定量発注方式」について説明する。 |
|
この方式はある決まった量を発注するため、使用量の変化により発注の時期は変動する。
下の図は定量発注方式の型を示したものである。 この方式で基本的に決定すべきものは、発注量と発注点(発注を行う必要が生ずる在庫量の水準)である。 この方式では、在庫量が発注点に達したとき、決められている発注量を発注することになる。 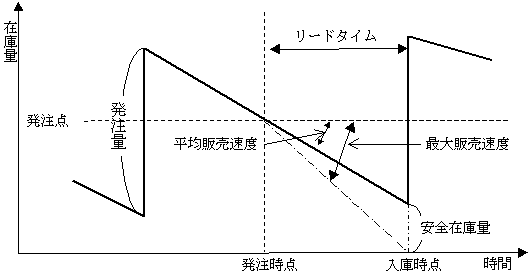 |
この方式は発注間隔が一定であり、発注量はリードタイム中の需要の総推定量・
発注済未入庫量・期末在庫・安全在庫などによって決定される。
下の図は定期発注方式の型を示したものである。ただし0<リードタイム<発注サイクルである。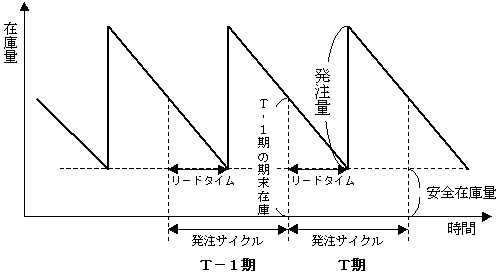 発注量は以下の式で示される。 |



